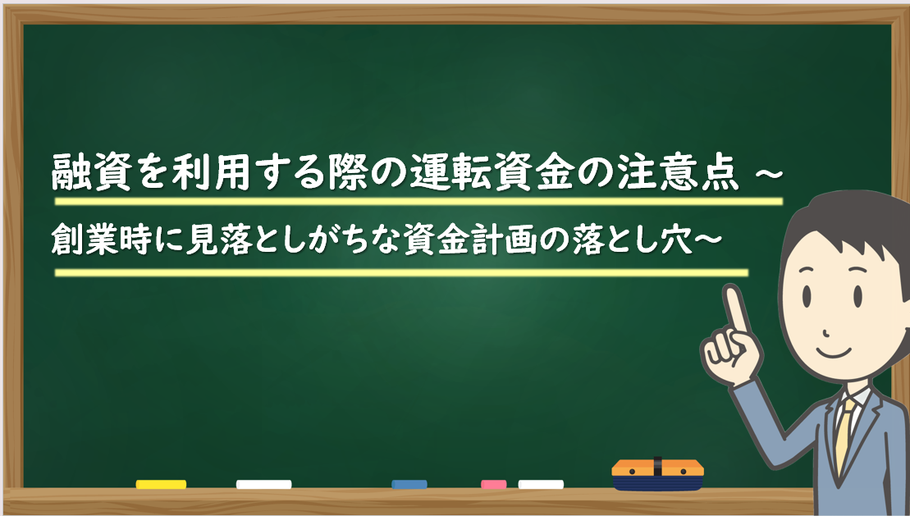
はじめに:運転資金は起業成功のカギを握る

創業時や事業拡大時において、日本政策金融公庫などの制度融資を利用する際、「運転資金」と「設備資金」のどちらを中心に借入を行うかは重要な検討事項となります。多くの起業家が、「できるだけ多くの資金を借りたい」「なるべく余裕を持った資金計画を立てたい」と考える一方で、実際には設備資金を中心とした計画の方が融資額が多くなりやすく、運転資金を中心とする資金計画では想定よりも少ない融資しか受けられなかったというケースも少なくありません。
この記事では、創業融資などで運転資金を借り入れる際の注意点や、審査に通るために重視すべきポイントについて解説します。
1. 設備資金と運転資金の違いを正しく理解する
まずは、「設備資金」と「運転資金」の違いを正確に理解することが大前提となります。
|
設備資金 |
店舗の内装工事費、機械設備、車両、パソコンや什器備品など、将来的に価値を持ち続ける“固定資産”の取得費用に該当します。使途が明確で、見積書や契約書などの証拠書類も用意しやすいため、融資審査の際には判断がしやすく、資金使途の裏付けも取りやすいといえます。 |
| 運転資金 | 仕入れ、外注費、人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費など、事業を継続的に回すために必要な日常の支出に充てる資金です。使途が多岐にわたり、使い方の自由度が高い分、融資する側にとっては「過剰な資金を借りようとしていないか?」という視点で慎重に審査されます。 |
このように、設備資金は“固定の費用で、支出時期も明確”、運転資金は“流動的な費用で、将来にわたり継続して発生する”という違いがあります。
2. なぜ運転資金メインの資金計画は借入額が低くなりがちなのか?

創業者が「できるだけ多くの資金を借りたい」と思っていても、融資審査の結果、設備資金メインの計画と比べて、運転資金メインの計画では借入希望額に満たないケースが多く見られます。その背景には、以下のような理由があります。
(1)金額の根拠を示しにくい
運転資金は「毎月これくらいかかるだろう」といった見積もりに基づくため、金額の根拠が不明確になりがちです。とくに創業直後では過去の実績がないため、「本当にその支出が発生するのか」「どのくらいの期間必要なのか」を審査側が判断しづらいのです。
(2)返済可能性の根拠が弱くなりやすい
審査担当者は、「この融資を実行した結果、事業は順調に進み、返済が可能かどうか」を重視しています。しかし、運転資金の多くは使ってすぐに回収される保証がないため、売上予測や利益計画との整合性が取れていないと「本当に返せるのか?」という懸念を抱かせてしまいます。
(3)資金使途が拡張解釈されやすい
例えば、「3ヶ月分の人件費として100万円」という計画にしても、他の用途に転用されてしまうリスクがあると判断されてしまうと、結果として希望額満額の融資は認められない可能性があります。
3. 運転資金を含む融資申請で重視されるポイント
では、運転資金を含む資金計画で審査を通過し、必要な金額の融資を受けるには、どのような点に気をつけるべきでしょうか。
(1)資金使途を具体的に説明する
運転資金も、「何に」「いつ」「どれくらい」使うかをできるだけ明確に記載しましょう。たとえば、
◆ 仕入資金・・・初月30万円、2ヶ月目以降毎月20万円
◆ 人件費・・・・・アルバイト1名・時給1,200円、月80時間稼働で9万6,000円/月
このように、支出項目を細かく分け、現実的な根拠を示すことで信頼性が高まります。
(2)売上・利益計画と整合性を持たせる
「どれくらい運転資金が必要か?」は、将来の売上や回収サイクルと密接に関係しています。
たとえば、「商品を30万円仕入れるが、売上は20万円しか見込めない」といった計画では、そもそも資金繰りが成り立ちません。審査担当者もこの点は非常に注視しているため、PL(損益計算書)やCF(キャッシュフロー計画書)と整合性が取れた資金計画を作成しましょう。
(3)回収サイト・支払いサイトのバランスに注意
売掛金の回収サイト(何日後に現金化されるか)と、仕入や外注費などの支払いサイト(何日後に支払うか)のギャップが大きくなると、資金繰りが厳しくなります。
運転資金を借りる際は、「サイト差によるキャッシュフローのズレがあるため、これだけの運転資金が必要である」といった説明ができると、納得感が高まります。
4. 設備資金とのバランスを考えた融資申込みが有効

上述の通り、運転資金は審査上のハードルがやや高いため、できれば設備資金と組み合わせた申請が効果的です。
設備資金は裏付け資料が揃いやすく、「この設備を導入することで事業がこう成長する」と説明しやすい分、より前向きな評価が得られます。設備資金がメインとなることで、事業の成長性・持続性が伝わりやすくなり、結果的に運転資金も必要額を含めて融資されるケースが多くなります。
5. 融資担当者はここを見ている

融資の可否を決める審査担当者が着目しているポイントを整理すると、以下の3点が特に重要です。
(1)事業の継続可能性
運転資金は「事業を続けるためのお金」です。つまり、事業が継続しなければ融資は回収できません。そのため、事業モデルの実現性・競合との差別化・顧客の見込みなどを含めた総合的な計画が求められます。
(2)資金計画の妥当性
「どれくらい必要で」「何に使うか」が具体的であるほど、信頼度が増します。金額が大きいからといって一律に否定されるわけではありませんが、適正さと根拠が重視されます。
(3)返済能力
融資はあくまで「借りたお金を返す」ものです。借入後の利益見込み、営業キャッシュフロー、既存借入とのバランスなど、返済能力の裏付けがしっかりあることが最終的な決め手になります。
おわりに:信頼性のある資金計画で、事業をより確実に
運転資金の融資を通すためには、「具体的で、整合性の取れた事業計画」を作成することが不可欠です。
とくに創業時は、事業そのものが未知数であるため、より丁寧な説明が求められます。
「設備資金と組み合わせて申請する」や「資金のサイト差を意識した資金繰りの考え方を伝える」、「売上・利益と矛盾のない支出計画を立てる」など、信頼性を高める工夫を積み重ねていきましょう。
融資はあくまで事業を成功させるための「手段」です。必要な資金を確保することで、安心して経営に取り組めるよう、万全の準備をして臨んでください。
✅無料相談受付中!
当事務所では、融資や補助金申請に関する無料相談を提供しています。専門家によるアドバイスを受けることで、融資の成功確率を高めることができます。オンライン相談は、初回のみ30分でご提供させていただきます。
現在考えている事業計画のブラッシュアップや資金調達の最適な方法を一緒に検討することができます。
「中小企業・個人事業者向け Zoom無料相談」はコチラ

神奈川県・横浜市・横浜市青葉区の事業者の方へ
~経営に関するお悩み事があればお気軽にご相談ください~
1,000社以上の支援経験のある代表が御社に最適なサポートをご提供いたします。

